カラス保護の統計 2025年版
当サイトでは、ケガをしたカラスを保護した人からの相談が多く寄せられている。
今回の「カラス保護の統計2025年版」は、2023年1月1日から2025年10月9日までの3年間に寄せられた233件のカラス保護相談を集計したものである(図1,図2を除く)。
「カラス保護の統計 2022年8月版」 ←第二版
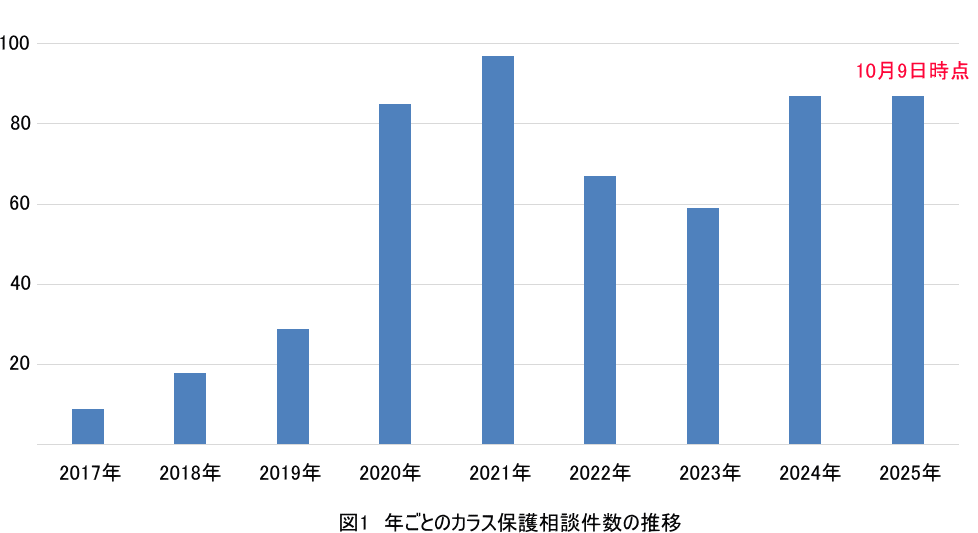
まず、当サイトが発足してから現在までのカラス保護相談件数を示す(図1)。
2020年から急激に相談件数が上昇したが、これはこの年からカラスを保護する人が増えたわけではなく、単に当サイトの知名度が上がった結果である。以前からカラスを保護する人は多くいたのだが、それが当サイトによって可視化されたのである。実際にカラスを保護した人は、これよりはるかに多くいると推測できる。
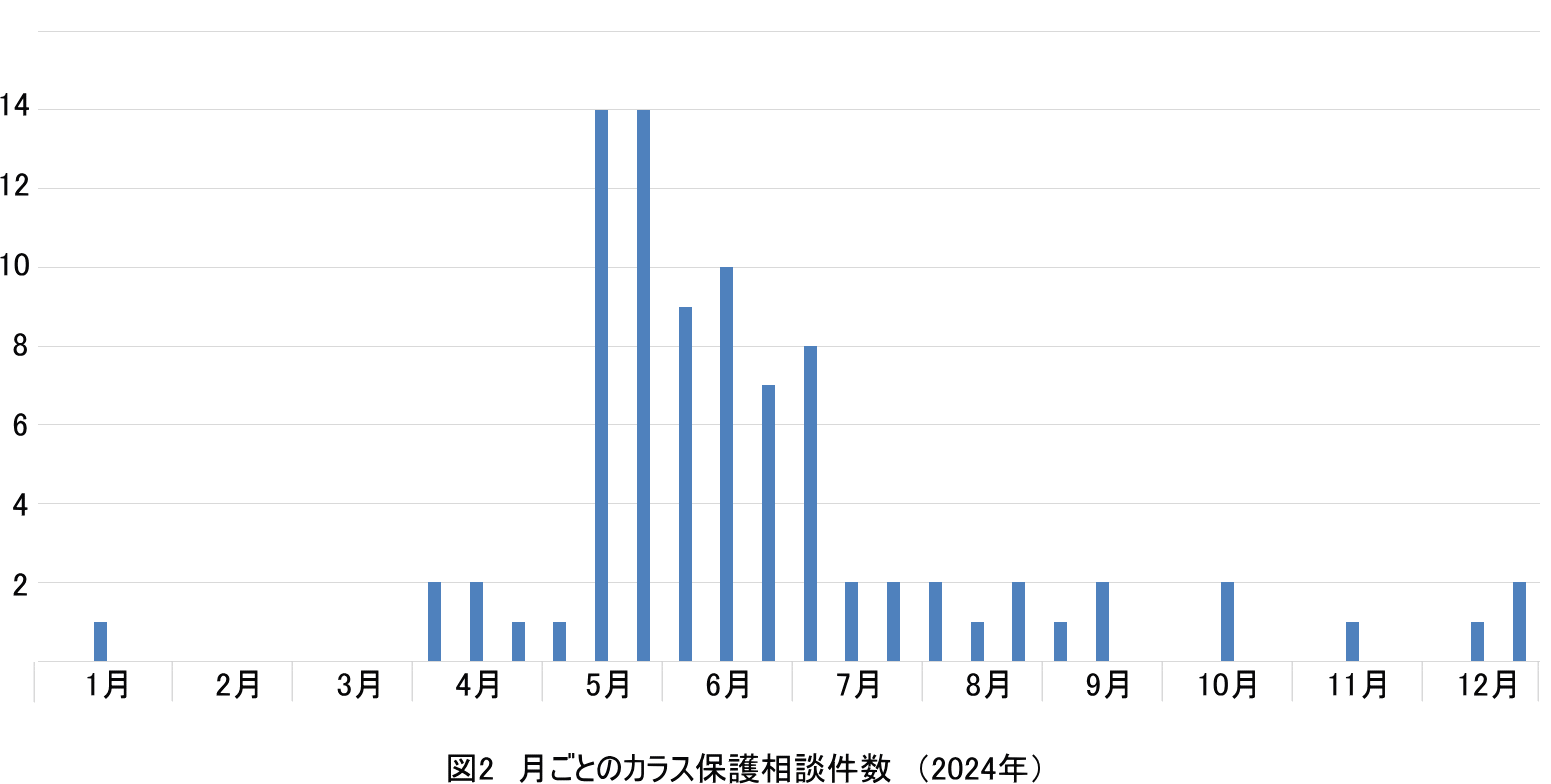
2024年の一年間を例にとり、相談件数を月ごとに示した(図2)。
当サイトには一年間に80件前後の相談が寄せられるが、その時期は5月と6月に集中している。この時期に相談が集中する理由は、巣立ちに失敗した雛鳥が多いということである。冬季に保護される事例もあるが、この期間は鳥獣保護管理法上の狩猟期間であり、合法捕獲に該当する事例もある。逆に言うと、狩猟期間外の保護は鳥獣保護管理法には何も記載されていないため合法とは言えず、法律の指針に書かれている傷病救護の規定だけが唯一の拠り所となる。
法律について、詳しくは「カラスと法律」で解説しているので、そちらを一読いただきたい。
保護されたときの状況
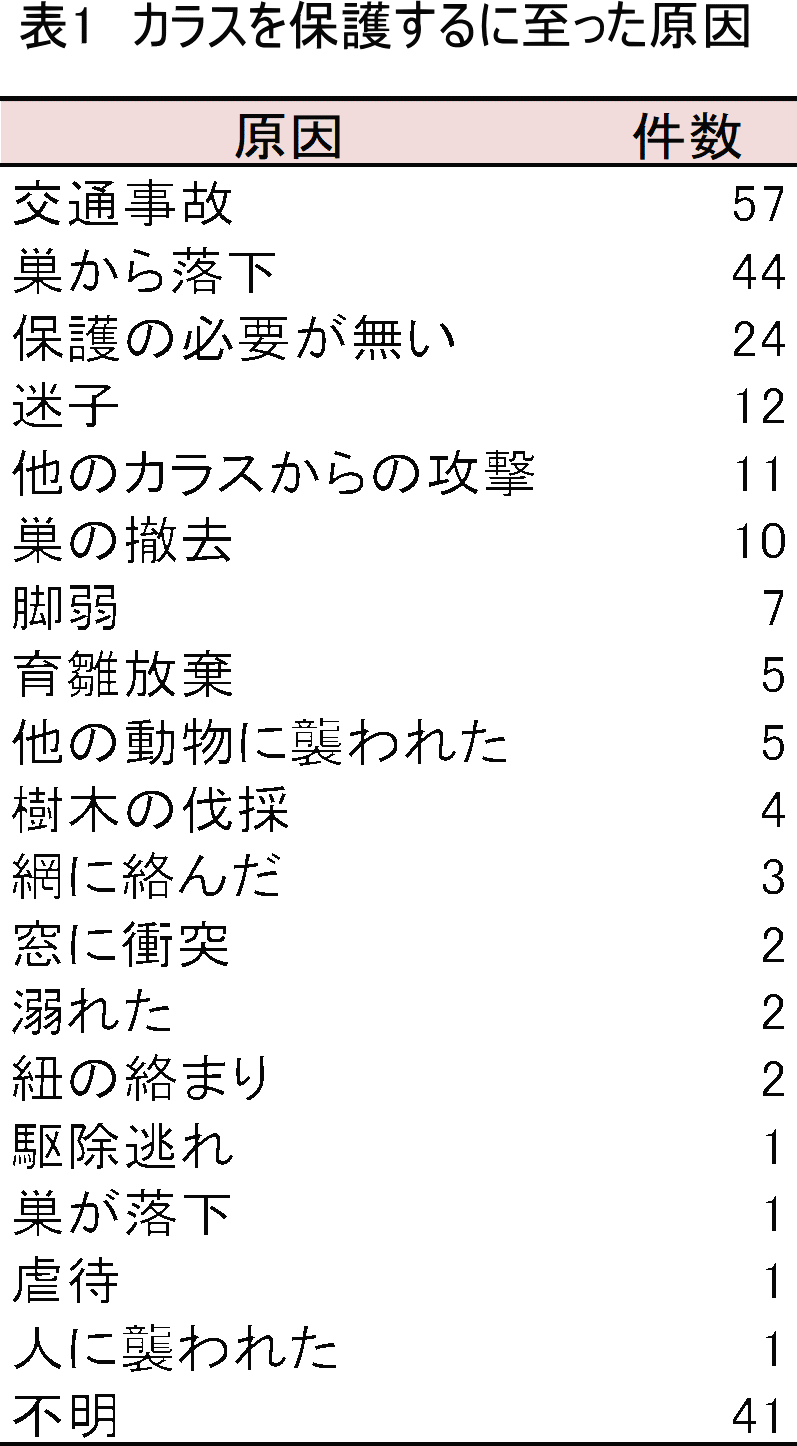
保護されたカラスたちはどのような状況だったのか、相談者から聞き取った状況を(表1)にまとめた。
明確に原因が分かっているもの以外は、保護時の状況から原因を推定したものも含まれる。例えば「交通事故」は、実際に事故に遭った現場を見たわけでなくても、骨格に激しい衝撃を受けた痕跡があれば交通事故と判定している。
カラスがケガをする原因として最も多いのは交通事故であるが、これは人間社会に溶け込んだカラスならではのものだ。交通事故といっても鳥の場合は車のタイヤに轢かれるよりも、飛翔中に車体と接触して翼を骨折する事例が多い。
続いて「巣から落下」であるが、カラスの場合は風切羽も伸びきらない日齢で巣から落下する雛は多い。理由は、縄張り争いに巻き込まれて他のカラスに落とされたり、襲われてパニックになり落下することもある。また、成長の悪い雛は親鳥によって巣の外に放り出されることもある。これはいわゆる間引きであるが、間引かれた雛は保護して育てたとしても、その後に死んだり障害が残ることが多い。
「保護の必要が無い」というのは、正常な巣立ち雛を傷病と誤認して保護した事例である。当サイトでは、このような事例に対しては親鳥の元に雛を戻すよう強くアドバイスしている。
カラスの場合、「巣の撤去」や「木の伐採」など、人為的に巣が破壊されることが多いのも特徴だ。ここにある巣の撤去などは駆除業者ではなく、捕獲許可を持たない一般人によるものが多い。それらはカラスを忌み嫌っての行動であるため、当然、放り出された雛をその人が救助することもない。相談が寄せられるのは、そのような時に地面に放り出された雛を救助した第三者からである。ちなみに、鳥獣保護法上の「捕獲者」は木を伐採、あるいは巣を撤去した人であるが、この時に放り出された雛を保護した善意の第三者が捕獲者に該当するのか法律は想定していない。常識的に考えれば、違法捕獲された動物の救護ということになるだろう。
「脚弱」という表現は元は養鶏業界の用語だと思うが、雛鳥の成長不良による歩行困難な症状の総称である。具体的にはクル病や神経障害など原因は多岐に渡るが、カラスの場合はカルシウム不足によるクル病が圧倒的に多い。
「不明」とは、相談内容から状況を推測できるほどの情報が無い場合だ。
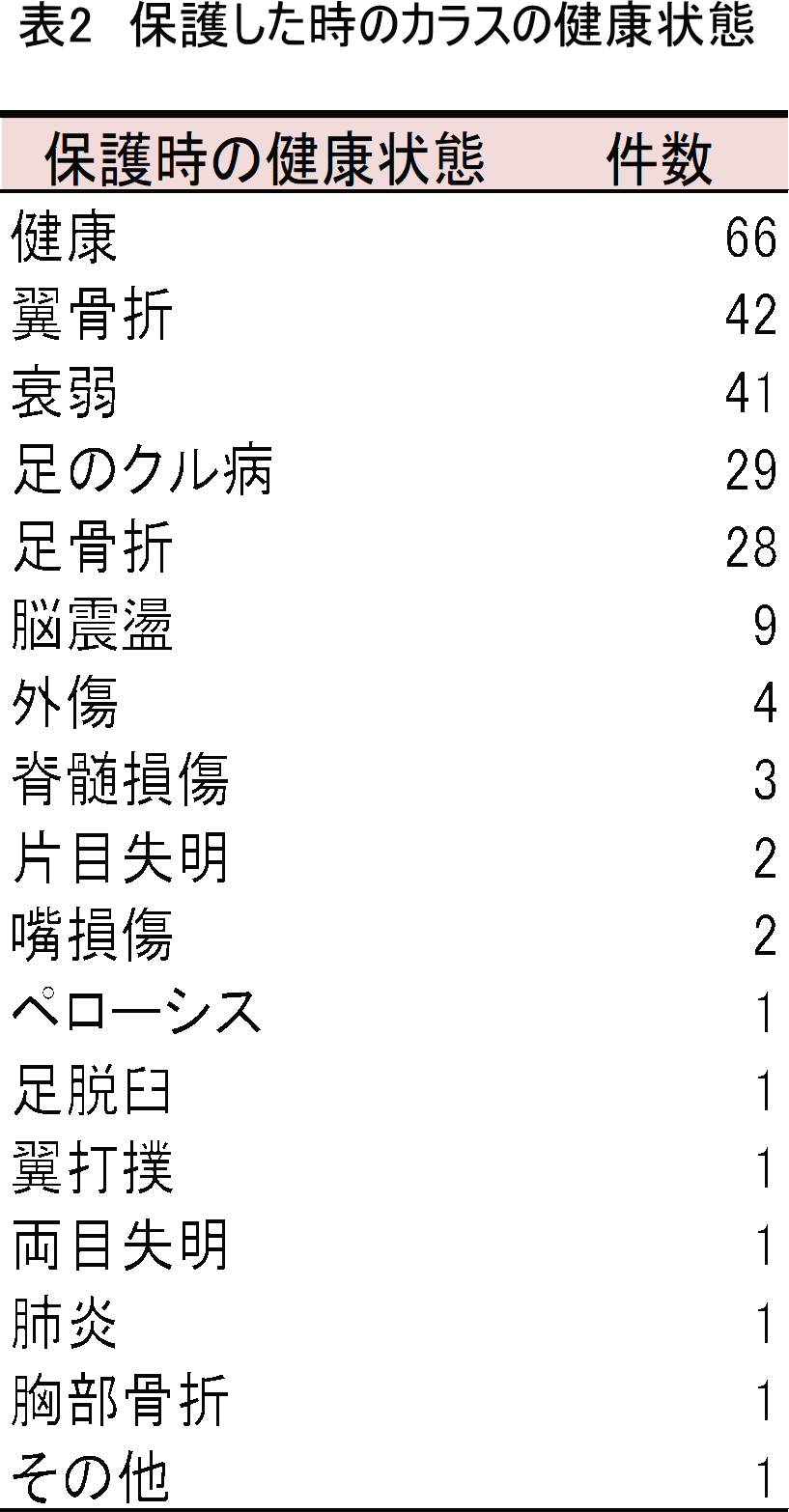
続いて、カラスが保護されたときの健康状態を(表2)に示す。
「健康」な個体が多いことが特徴だが、これは先程示した保護時の状況とだいたいリンクするだろう。「巣の撤去」や「正常な巣立ち雛との誤認」の他、巣立ち前の未発達の雛が巣から落ちる事例が多い。その際にケガをしていなければ「健康」と判定している。健康といっても、風切羽も伸びていない日齢の雛が地面で育つことはない。その状況では親鳥が落下した雛の育雛を諦めることが多く、あるいは先述のとおり親鳥自身が育ちの悪い雛を間引きした可能性もあるからだ。当然、その雛は死ぬ運命にあるが、自然界の掟を尊重するならこの状況で助ける必要はないだろう。だが、通りがかりの一般人がそのように割り切った考えや理念を持ち合わせているわけではないので、助けなければと衝動的に手を差し伸べるのである。そもそも、山野での出来事なら自然界の掟であるが、公園や自宅の庭など人間が構築した環境で起きることは自然界の掟とは言えないだろう。
続いて多いのが「翼の骨折」であるが、先述のとおり、ほとんどの原因は交通事故である。「脳震盪」と「脊髄損傷」も交通事故が原因であることが多い。交通事故は自然界での出来事ではないため、保護して治療したうえで放鳥することが望ましいだろう。しかし、脚はともかく翼の骨折は完治しないことが多い。さらに、脊髄損傷については治療はほぼ無理であり、保護しても要介護状態になるか、たいていは数日で死に至る。
「衰弱」の状態で保護されるのはほとんど幼鳥である。幼鳥は自力で採餌できないため、親鳥とはぐれて迷子になった場合は生きていくことはできない。そのような幼鳥は保護した時点で脱水症状を起こしていることが多い。食欲もない場合は極めて危険であるが、まずは水分補給と保温により回復を待つ。雛鳥の成長速度は極めて速いため、この期間の栄養不足は致命的な結果になることが多い。実際に、衰弱した幼鳥の多くはその後、数日で死亡している。
「クル病」はカラスの雛によく見られる症状で、栄養不足により骨格の成長が進まず、関節が変形したり骨が湾曲する(若木骨折)などの症状が現れる。クル病の雛は骨密度が低いため、症状は脚だけにとどまらない。そのため少しの衝撃で脊椎を脱臼することがある。そうなると脊髄の神経が圧迫されて下半身が動かなくなり、影響は内臓にまで及び、やがて死に至る。クル病は幼鳥期なら適切な栄養摂取で改善することもある。
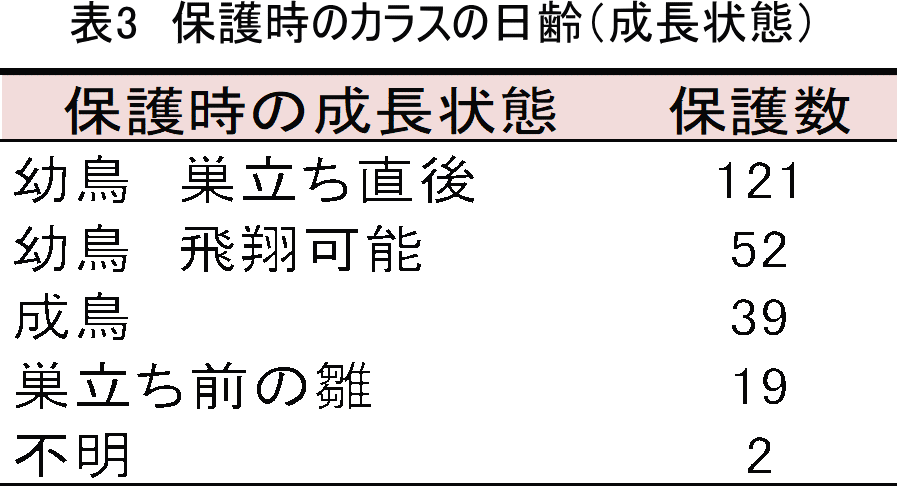
保護されたカラスの保護時点での年齢を見てみると、巣立ち前後の飛べない幼鳥が多いことが分かる(表3)。巣立ちの日齢に達する前に巣から落下する事例が多いことは先述のとおりだが、それ以外においても飛べない状態のまま巣立ちすることが多いこともカラスの特徴である。鳥の巣立ちというと、雛が順番に巣から颯爽と飛びたつ感動のシーンを思い浮かべるかもしれないが、街中におけるカラスの巣立ちは、飛び立つというより真下に落下することの方が多い。そのため、飛べない雛が地面にいたとしても安易に手を出すべきではなく、親鳥の動向を注視するべきだ。巣立ち雛が車に轢かれそうなな場合は、親鳥の監視できる範囲内(縄張り内)で安全な場所に雛を移動させても構わない。
保護されたカラスの種類
日本に定着しているカラスは主にハシボソガラスとハシブトガラスの二種類だが、保護されるカラスはどちらが多いか見てみよう。
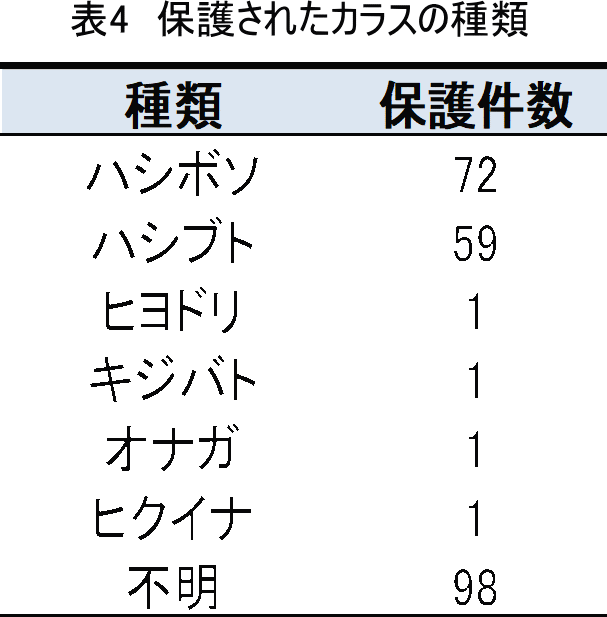
街で見かけるカラスは最近ではハシブトガラスの方が多いが(地域によって異なる)、それにもかかわらず保護されるカラスはハシボソ55%、ハシブト45%であり、ハシボソの方がやや多い。これを単純に解釈するとハシボソの方が巣立ちの失敗が多いといえるが、理由は幾つか考えられる。一つは、ハシボソの方が巣立ちの時期がやや早いため(5月頃)、その時期に栄養価の高いエサ(昆虫など)が少なく育ちが悪い可能性と、もう一つは、ハシブトの雛の方が大型であるため、それに伴い生命力が強くハシブトは巣立ちの失敗が少ないのではないか、などの理由が考えられる。
(表4)にはカラスではない鳥が混ざっているが、多くは「カラスの雛と思われる」という相談である。鳥に興味が無い人にとっては、羽毛が揃わない雛鳥の最終形態は想像できないものだ。ここで注意が必要なことは、(表4)にあるキジバトやヒヨドリなどの狩猟鳥獣以外は、飼育していること自体が違法ということだ。そのような場合は地域の動物保護施設等に相談するか、相談先が無い場合は育てて放鳥するようアドバイスしている。日本野鳥の会などが推進する「雛を拾わないでキャンペーン」の影響と思われるが、役所は野鳥の保護に対して非常に冷たい対応しかしない。どのような状況においても「元の場所に返しなさい」とだけ指示するのが通例である(希少動物種を除く)。
「不明」が圧倒的に多いが、これは相談者がハシブトとハシボソを区別することなく「カラス」と表現する場合だ。相談者に「種類はどちらですか?」と聞いても分からないことが多い。それまでカラスに興味が無かった人にとって、ハシブトもハシボソも同じカラスという認識であり、さらに、雛鳥の時点では両者の特徴が分かりにくいこともある。
保護されたカラスたちのその後
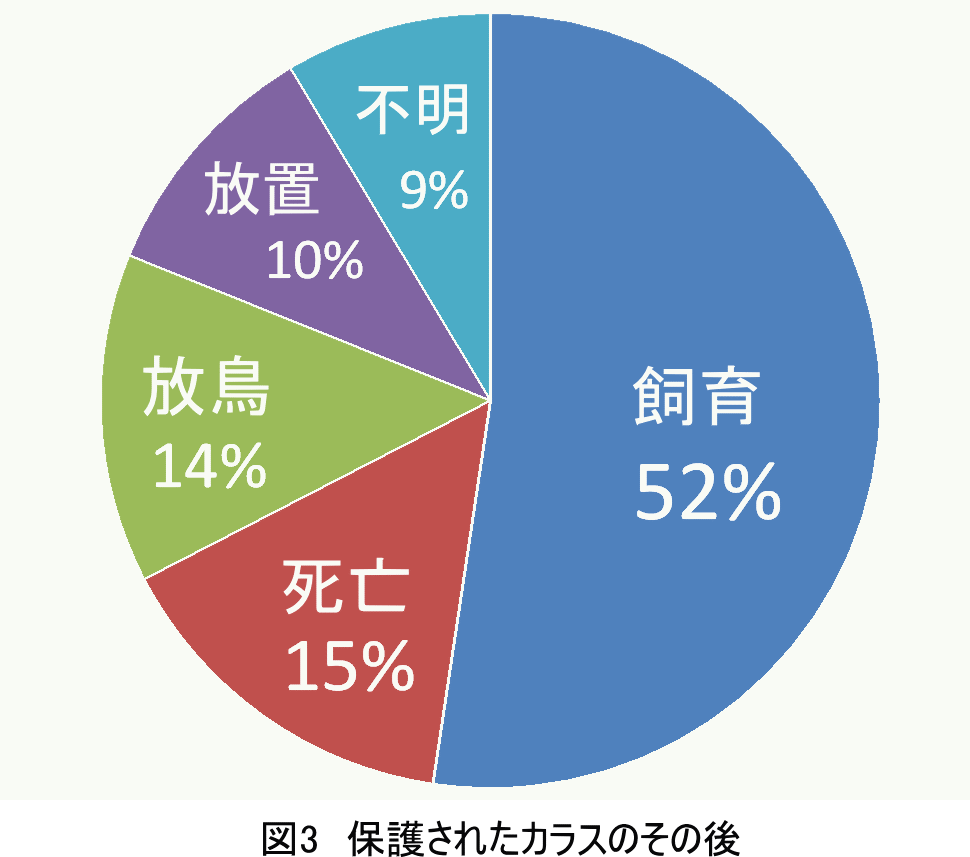
こうして保護されたカラスたちはその後どうなったのか、(図3)に示す。
「飼育」が半数以上にのぼるが、しかし、カラスを飼い続けられる環境を持った人がそれほど多くいるわけではない。当サイトでは、その後の聞き取り調査までは積極的におこなっていないので、このなかには後に放鳥に至った事例が相当数含まれるはずである。あるいは、保護した幼鳥はその年の冬を越せないことが多いため、何割かは死んだと推測している。保護した幼鳥がその年の冬に死ぬことが多い理由だが、人が育てたカラスは免疫が完全に備わらず、感染症に掛かりやすいことが原因の一つと考えられる。また、衰弱状態で保護した雛の場合、成長期に絶食を強いられたことになるため、これが後に致命的な不調をもたらすことが考えられる。このような事情があるため、(図3)にある「飼育」のうち半数以上は「放鳥」と「死亡」に振り分けられるとみるべきだろう。
「放置」というのは、保護相談を受けた時点でまだ保護に至っていないときに、保護せずに見守るようアドバイスした事例である。
以上、3年間、233件分のデータを集計したものだが、これはカラス本来の行動や生態を表しているものではなく、あくまで人間社会におけるカラスの状況を示したものである。
更新履歴
2025年10月19日 公開
- 都庁に拉致されたカラス 必読!
- 里親募集199 里親決定
- 里親募集198 里親決定
- 里親募集197 里親決定
- 里親募集196 里親決定
- 里親募集195 里親決定
- 里親募集194 里親決定
- 里親募集193 里親決定
- 里親募集192 交渉中
- 里親募集191 里親決定
- 里親募集190 里親決定
- 里親募集189 里親決定
- 里親募集188 里親決定
- 里親募集187 里親決定
- 里親募集186 募集終了
- 里親募集185 里親決定
- 里親募集184 里親決定
- 2026年1月18日 New!
- 2025年12月31日
- 2025年12月14日
- 2025年11月30日
- 2025年11月24日
- 2025年11月16日
- 2025年11月3日
- 2025年10月29日
- 2025年8月24日
- 2025年8月10日
- 2025年7月27日
- 2025年5月25日
- 2025年5月18日
- 2025年5月11日
- 2025年5月4日
- 2025年4月13日
- 2025年3月30日
- 2025年2月23日
- 2025年1月26日
- 2025年1月19日
- 2024年12月21日
- 2024年12月15日
- 2024年12月01日
- 2024年11月24日
- 2024年10月20日
- 2024年9月29日
- 2024年9月16日
- 2024年9月1日
- 2024年8月12日
- 2024年7月28日
- 2024年7月21日
- 2024年7月6日
- 2024年6月23日
- 2024年5月26日
- 2024年5月19日
- 2024年5月6日
- 2024年4月29日
- 2024年4月14日
- 2024年3月24日
- 2024年3月10日
- 2024年3月3日
- 2024年2月12日
- 2024年1月21日
- 2024年1月8日
- 2023年12月31日
- 2023年12月10日
- 2023年11月19日
- 2023年11月12日
- 2023年10月29日
- 2023年10月15日
- 2023年10月1日
- 2023年9月3日
- 2023年8月27日
- 2023年8月20日
- 2023年8月13日
- 2023年7月30日
- 2023年7月16日
- 2023年7月2日
- 2023年6月25日
- 2023年6月11日
- 2023年5月28日
- 2023年5月14日
- 2023年4月30日
- 2023年4月16日
- 2023年4月9日
- 2023年3月26日
- 2023年3月5日
- 2023年2月19日
- 2023年2月12日
- 2023年2月5日
- 2023年1月22日
- 2023年1月15日
- 2023年1月8日
- 2022年12月24日
- 2022年12月4日
- 2022年11月20日
- 2022年10月29日
- 2022年10月23日
- 2022年10月9日
- 2022年9月25日
- 2022年9月11日
- 2022年8月29日
- 2022年8月14日
- 2022年7月31日
- 2022年7月17日
- 2022年7月10日
- 2022年7月3日
- 2022年6月19日
- 2022年6月12日
- 2022年6月5日
- 2022年5月29日
- 2022年5月12日
- 2022年5月5日
- 2022年4月17日
- 2022年4月3日
- 2022年3月21日
- 2022年3月6日
- 2022年2月13日
- 2022年1月30日
- 2022年1月16日
- 2022年1月9日
- 2021年12月26日
- 2021年12月19日
- 2021年11月28日
- 2021年11月21日
- 2021年11月6日
- 2021年10月24日
- 2021年10月10日
- 2021年9月26日
- 2021年9月19日
- 2021年9月11日
- 2021年9月5日
- 2021年8月22日
- 2021年8月1日
- 2021年7月18日
- 2021年7月11日
- 2021年7月4日
- 2021年6月13日
- 2021年6月6日
- 2021年5月30日
- 2021年5月23日
- 2021年4月25日
- 2021年4月11日
- 2021年3月28日
- 2021年3月2日
- 2021年2月21日
- 2021年1月31日
- 2021年1月24日
- 2021年1月17日
- 2021年1月1日
- 2020年12月20日
- 2020年11月29日
- 2020年11月15日
- 2020年11月1日
- 2020年10月17日
- 2020年9月19日
- 2020年9月13日
- 2020年9月6日
- 2020年8月25日
- 2020年8月16日
- 2020年8月9日
- 2020年7月26日
- 2020年7月19日
- 2020年7月12日
- 2020年6月27日
- 2020年6月7日
- 2020年5月24日
- 2020年5月16日
- 2020年5月2日
- 2020年4月26日
- 2020年4月20日
- 2020年4月13日
- 2020年3月30日
- 2020年3月23日
- 2020年3月15日
- 2020年3月8日
- 2020年2月23日
- 2020年2月2日
- 2020年1月26日
- 2020年1月19日
- 2020年1月3日
- 2019年12月29日
- 2019年12月23日
- 2019年12月22日
- 2019年12月15日
- 2019年12月14日
- 2019年11月24日
- 2019年11月17日
- 2019年11月16日
- 2019年11月9日
- 2019年10月26日
- 2019年10月19日
- 2019年10月6日
- 2019年9月29日
- 2019年9月22日
- 2019年9月8日
- 2019年9月3日
- 2019年8月25日
- 2019年8月18日
- 2019年8月12日
- 2019年8月4日
- 2019年7月28日
- 2019年7月20日
- 2019年7月14日
- 2019年6月30日
- 2019年6月23日
- 2019年6月17日
- 2019年6月9日
- 2019年5月26日
- 2019年5月13日
- 2019年5月4日
- 2019年4月29日
- 2019年4月14日
- 2019年4月6日
- 2019年3月31日
- 2019年3月16日
- 2019年3月10日
- 2019年3月3日
- 2019年3月2日
- 2019年2月10日
- 2019年2月9日
- 2019年1月13日
- 2019年1月1日
- 2018年12月30日
- 2018年12月23日
- 2018年12月16日
- 2018年12月9日
- 2018年12月2日
- 2018年11月26日
- 2018年11月18日
- 2018年10月28日
- 2018年10月21日
- 2018年10月14日
- 2018年10月7日
- 2018年9月30日
- 2018年9月24日
- 2018年9月16日
- 2018年8月19日
- 2018年8月11日
- 2018年7月22日
- 2018年7月15日
- 2018年7月14日
- 2018年7月8日
- 2018年7月1日
- 2018年6月24日
- 2018年6月3日
- 2018年5月27日
- 2018年5月22日
- 2018年5月13日
- 2018年5月10日
- 2018年4月28日
- 2018年4月22日
- 2018年4月8日
- 2018年4月3日
- 2018年3月25日
- 2018年3月17日
- 2018年3月11日
- 2018年3月4日
- 2018年2月18日
- 2018年2月3日
- 2018年1月28日
- 2018年1月13日
- 2017年12月31日
- 2017年12月24日
- 2017年12月17日
- 2017年12月10日
- 2017年12月3日
- 2017年11月19日
- 2017年10月30日
- 2017年10月22日
- 2017年10月15日
- 2017年10月3日
- 2017年9月24日
- 2017年9月6日
- 2017年8月6日
- 2017年7月29日
- 2017年7月17日
- 2017年7月16日
- 2017年7月9日
- 2017年7月2日
- 2017年6月25日
- 2017年6月17日
- 2017年6月11日
- 2017年6月5日
- 2017年5月28日
- 2017年5月21日
- 2017年5月13日
- 2017年5月6日
- 2017年4月30日
- 2017年4月23日
- 2017年4月15日
- 2017年4月9日
- 2017年3月26日
- 2017年3月12日
- 2017年3月5日
- 2017年2月18日
- 2017年2月11日
- 2017年2月5日
- 2017年1月29日
- 2017年1月22日
- 2017年1月15日
- 2017年1月3日
